ディズニー映画『リトル・マーメイド』(実写版)のアリエル役に黒人女性が起用されたことに対し、世界では賛否が分かれました。
この抜擢に対する海外の反応を調べました。
『リトルマーメイド』のアリエル役に黒人女性起用!海外の反応は?
1989年に上映されたディズニーの『リトル・マーメイド』はアニメだったのですが、主役は白人の女性として描かれていました。

https://getnews.jp/archives/2168802/gate
それから34年後の2023年に、同じディズニーが『リトル・マーメイド』の実写版を制作します。
そこで主役に抜擢されたのが黒人女性歌手のハリー・ベイリー。

https://www.vogue.co.jp/article/halle-bailey-to-keep-natural-hair-in-the-little-mermaid
この起用に世界では賛否が分かれます。
CNN.co.jpの記事を基に、海外の反応を地域ごとに分けて整理すると、以下のようにまとめることができます。
| 地域 | 含まれる国 | 主な反応 |
|---|---|---|
| 北米 | アメリカ合衆国、カナダ | 公開後初めての週末で高い興行収入を記録。主演女優ハル・ベイリーの歌声や演技力が賞賛される。 |
| ヨーロッパ | イギリス、ドイツ、イタリア、フィンランド | イタリアでトップ、ドイツや英国で好調。フィンランドでも高い集客力を示す。 |
| 中東 | アラブ首長国連邦(UAE) | UAEで高い集客力を誇る。 |
| オセアニア | オーストラリア | オーストラリアで高い興行収入を記録。 |
| 東アジア | 日本、中国、韓国 | 日本と中国、韓国では批判的な意見が多く、興行収入も振るわなかった。 |
| 東南アジア | インドネシア、フィリピン、シンガポール | インドネシアが410万ドル、フィリピンが440万ドルの興行収入を収め、高い集客力を記録。シンガポールでも好評。 |
| 南米・中米 | ブラジル、メキシコ | ブラジルとメキシコで2位の興行収入。 |
このCNNの記事によると、本国のアメリカを含めて世界中で興行収入が良かった一方で、東アジア(日本・韓国・中国)では興行収入が振るわなかったとあります。
むろん、北米やヨーロッパでも、黒人女性をアリエル役に起用したことに対して人種差別的なバッシングはあったようです。
ただ、興行収入が明確に低迷したのは日本・中国・韓国だったんですね。
Wikipediaでは、中国共産党の機関紙『環球時報』がこのキャスティングを批判したとあります。
In May 2023, an editorial from Chinese state-run tabloid Global Times accused Disney of “forced inclusion of minorities” and “lazy and irresponsible storytelling”, echoing the views of some social media users in China, Japan, and South Korea. The Global Times similarly attributed the film’s poor performance in China to “Disney turning classic tales into ‘sacrificial lambs’ for political correctness.”
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Little_Mermaid_(2023_film)
日本語に訳すと、
2023年5月、中国の国営タブロイド紙『環球時報』は、ディズニーが「少数派の包摂を強制している」「怠惰で無責任なストーリーテリング」を行っていると非難する社説を掲載した。この意見は、中国、日本、韓国の一部のソーシャルメディアユーザーの見解とも一致している。『環球時報』は、ディズニーが「政治的正しさ(ポリティカル・コレクトネス)のために古典的な物語を”生贄”にしている」として、中国における同映画の不振の原因もこれにあると指摘した。
となります。
党の機関紙がポリティカル・コレクトネス(通称:ポリコレ)を公然と批判しているのがすごいですよね。
『リトルマーメイド』に対する海外の反応〜東アジアで不評だった3つの理由
実写版『リトル・マーメイド』の興行収入がなぜ東アジア(日本・中国・韓国)では不振だったのか?
日本・中国・韓国では主役のアリエル役に黒人女性が起用されたことに対して、SNSでも強い反応を引き起こしました。
X(旧Twitter)では「#NotMyAriel(私のアリエルじゃない)」というハッシュタグが拡散されたぐらいです。
ただ、シンガポール、フィリピン、インドネシアでは興行収入が良く、黒人女性がアリエル役になったことに対しても特に批判は起きなかったんです。
同じアジアなのに、なぜこのような差が生じるのか?
いくつか理由がありそうです。
アニメ版のイメージが変わることへの抵抗感
1989年に公開されたディズニーのアニメ版『リトル・マーメイド』は、日本・韓国・中国でも非常に人気がありました。
アニメ版のアリエルは「白い肌に赤毛」というビジュアルで、そのイメージが定着したんです。
日中韓ではキャラクターのビジュアルイメージを重んじる傾向があり、一度定着したイメージが変わることへの抵抗が大きいんですね。
そのため、「リメイクは原作に忠実であるべき」という考えが強く、原作のイメージを改変するとバッシングが起きやすいと言えます。
東アジアの今回の拒否反応は、主役が黒人女性になったからというより、イメージそのものが変わってしまったことに対するものだったのかもしれません。
ポリティカル・コレクトネス(ポリコレ)への反発
欧米では多様性を重視する流れが強まり、ディズニーもそれに沿ったキャスティングを行うようになりました。
しかし、東アジアでは「ポリティカル・コレクトネス(政治的正しさ、通称「ポリコレ」)」の概念がそれほど浸透していません。
そのため、「ポリコレでキャスティングが決まったのでは?」「実力ではなく人種的な理由で選ばれたのでは?」という懐疑的な見方をする人が多いんですね。
『環球時報』が「少数派の包摂を強制している」と批判した背景には、このような見方が影響していそうです。
多様性に対する考え方の違い
先述のとおり、シンガポールやフィリピン、インドネシアの興行収入は好調でした。
これは、これらの国が多民族・多文化社会であることと関係がありそうです。
シンガポールは華人・マレー系・インド系が共存する多民族国家です。
インドネシアもジャワ人、スンダ人、バタック人、ミナンカバウ人、バリ人などから成る多民族国家です。
また、フィリピンは長年アメリカの支配下にあるため、欧米の価値観を受け入れやすい土壌があります。
一方、日本・韓国・中国はそれぞれ民族的に同質性の高い集団であり、多様性を欧米ほど重視しません。
そのため、映画を通して「欧米の価値観を押し付けられている」と感じやすいのかもしれません。
実際、欧米では多様性を前面に押し出すプロモーションが受け入れらましたが、日本・中国・韓国では逆効果になりました。
『リトルマーメイド』に対する海外の反応〜まとめ
実写版映画『リトル・マーメイド』のアリエル役に黒人女性であるハリー・ベイリーが抜擢されたことに対する世界の反応を見てきました。
とりわけ東アジアで興行収入が振るわなかった理由を3つの観点から考察しました。
参考になれば幸いです。

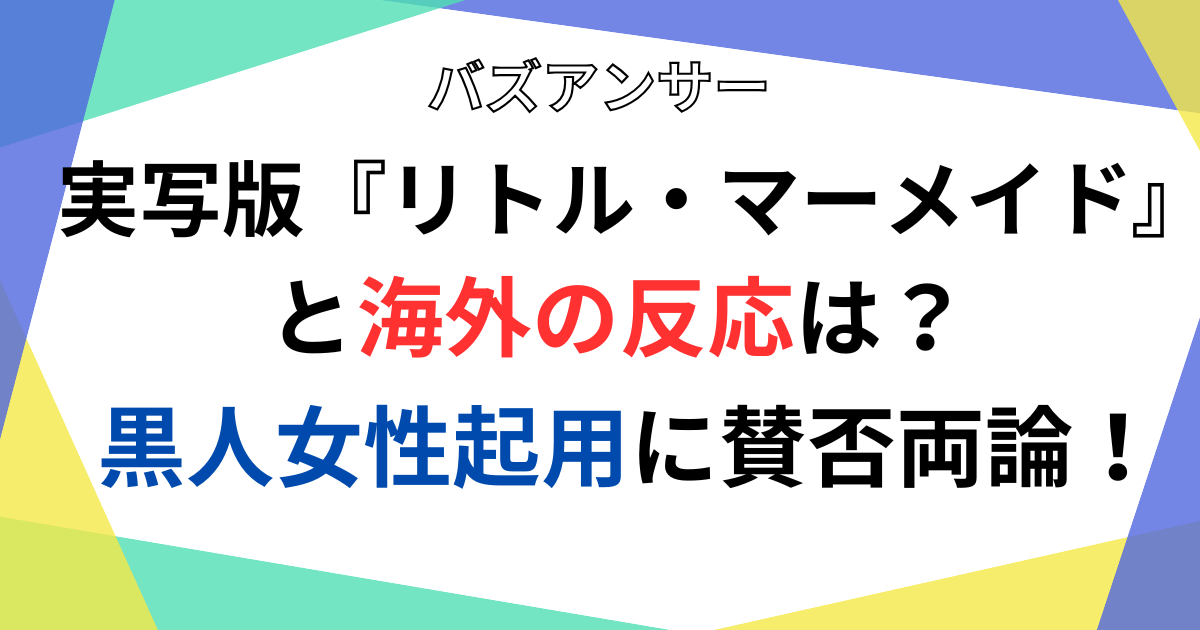


コメント